續.渺茫なる春嵐の向こうに
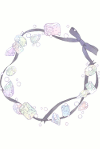
***
(そこから見つかった、ひとつの文に綴られていたのは、以下の内容だった。その文は何故か、以降に渡って少女の家で代々受け継がれ続けている。家宝と呼ぶには遠く、至宝と名指すには歴史も浅く、執筆者が穂波龍子である以外には何の情報もない。燃えれば忽ち灰となり、この世から消え去るだろうけれど、それを誰かが嘆くわけでもない。穂波龍子──旧姓、四賀龍子とは、別段。歴史上に登場する人物等でもなかった。)
大正 月──(以降は文字が霞んでおり、誰に宛てられたものか定かではない。)
冬の寒さもすっかり落ち着き、鶯が鳴くようになりました。梅の花が綻び、軈ては散る気配を漂わせております。愈々春も間近と迫り、能々歩くようになった道中に植えられている桜の木にも、膨らむ蕾があることに、この前ふとして気がつきました。
凍えるような冬は、今年ばかり意地の悪さを見せつけるようで、愛しいあの子を囲う籠の中は冷え冷えしておりました。
冷気は床を這うものですから、ストォブというものを置いてあげたかったのだけれど、あの子の眸はすっかり世界を見詰められなくなってしまっているものだから、火傷でもしたら一大事と、終ぞストォブを置いてやることは叶いませんでした。
あの子は春を迎える前に逝ってしまいました。春の桜の蕾が膨らんでいることに、気がついたその日のことでした。
以前よりあの子は言っていたの。「わたくしが、一番美しい日に──あなたの手で、殺めて欲しいの。」と。あの子が一番美しかったのは、桜の蕾が膨らんでいた、あの日だったのよ。
愛しいあの子は、いつでも愛らしく、盲目的なまでにあたくしを愛してくれているようでした。そうしてあたくしも、盲目的なまでに、あの子を愛しておりました。良人を好いたことは一度もなく、故に迫られても、何事も避け続ける日々。御家の者達は皆が揃ってあたくしとあの子を白い目で見ておりましたけれど、それが何だというのでしょう。あたくしは確かに外界と繋がるだけの身体能力を持っていたけれど、ただのそれだけ。それは、あたくしとあの子の世界を維持していく為に、必要なものでしかなく、必要な手段でしかなく、あたくしの世界にはあの子さえいれば、何もいらなかったのよ。
先にお断りしておきますけれど、これは断じて殺人では御座いません。光を失ったあの子の、目となり手となり足となり、あの子の光となり、あの子の世界となること。──あの子の望みは、どんなものでも叶えてあげるのが、あたくしにできる唯一にして最後の約束。ならばあの子の望む通りに、あの子を殺める以外に道は御座いませんでした。
けれどあの子は、あたくしにとっての世界。ならば世界を失ったあたくしが、外界で生きていくなど出来よう筈もなしに。「あたくしも、あなたのすぐ後に続きましょう。だからどうか、黄泉の国への淵際にて、待っていて頂戴ね。」こう、お返事を致しました。
そろそろあの子も待ち草臥れている頃でしょうから、逝ってあげなければね。もう一日も待たせてしまったのだから、不貞腐れているかもしれないわ。
さようなら、外界の皆様。良人とは形ばかりであった人。あたくしは、あの子と共に参ります。今度こそ、誰にも邪魔をされない、しがらみもない、二人だけの世界へ。あの子の眸に視力が戻り、もう一度あたくしを見て、微笑み、抱き合える世界へ。
穂波龍子(旧姓:四賀龍子)
(少女はこの文を家から持ち出し、と或る郷土資料館を訪れていた。どのようにしてこの女が死に至ったのか、それを知る者は既に誰もいない。──その頃には、青酸カリを使った心中というものが、一時ばかり流行ったそうだ。ならばこの女もまた、そうして心中したのかもしれない。────そうして少女は、持ち出した文を管理人に提示した。「この人が、ここで写真を撮ったかもしれないんです」必死な声音に、管理人は秘密の部屋の扉を開けてくれるらしかった。そこで少女は見つける。手にした文を綴った人物を。「嗚呼、きっとこの人だ。この二人のうちの、こっちの──、」直感的に察する。愛らしい少女と、勝気な調子の少女。写真は物言わず、されども二人の仲を睦まじいものであると、言葉なき言葉で伝えていた。)
(────ひとみが宝石のように変わっていく病があるらしい。玉眼症。多感期の最中に在る、十代の少女のみが発病することのある病なのだと聞いた。その治療法は未だ確立されておらず、初恋を諦めるという以外に、進行を止める術もないのだという。写真館を訪れた、名もなき少女の眸はちくり、時折として光に痛んだ。目頭が熱くなるような想いもした。不意にして見詰めた鏡の向こう側、映る己の眸の色に、仄かな異色の彩が添えられ始めていることを、少女は既に知っていた。──病は消えない。初恋という言葉が消えないことと、同じ道理だ。いのちみぢかし、こいせよおとめ。さりとてその恋を知れば、時には苦悩の日々を送るに至るだろう。けれども、恋も知らずに老いて朽ちるよりは幸いか。────それを決めるのは、読者のあなたではない。物語の主人公である、いつの時代でも清らかな、美しい花園に住まう乙女たちなのである。)
Published:2018/12/29 (Sat) 22:15 [ 36 ]