續.渺茫なる春嵐の向こうに
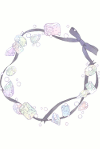
***
(私の瞳が光を映さなくなってどれくらい経っただろう。家の離れに建てられた新しい鳥籠の、真新しい木材と皮革のにおいもすっかり目立たなくなった。庭の木々を揺らす風は冬から目覚めて新しい春の香りを纏いはじめ、開け放たれた窓辺のカーテンを揺らす。学園を離れることの対価に与えられたものは過不足のない生活と、"いない筈の娘"という不便な立場だった。対外的に私は今、欧州へ遊学していることになっているらしい。公爵家の血族が不治の病を患っているなどというのはさぞ外聞が悪いのだろう。せめてもの慰めにと宛がわれた手伝いの女の一人は、年のころが近くて幾分おしゃべりな嫌いがあって、人形じみた鳥籠の主に物怖じしないところが誰かに似ていた。表向き大切にされている。外のことは知らない。それでも、治療法が見つかるか、娶る猛者が現れるか、それとも愈々病が回って死ぬか――周りがいずれかを待っているのは雰囲気でも知れた。過不足は何もない。穏やかに生かされている。呪いを恐れる者も、私を虐げる者もいない。私はただ生きている。)
(――夜半、あるいは夜明け前。時を知る術のない盲目には時間の経過も杳として知れない。目が覚めたのは、きっと必然だった。しじまに耳を澄ませれば、深々とした静けさが闇の濃さを教えてくれる。時折そうしていたのは、或いは何かを期待してのことだったのかもしれない。こつりと響いた音に、疑念の一つも浮かばなかったのも、きっと。窓を開け放てば、夜の空気とどこか懐かしい香りが鼻腔を掠める。――嗚呼、ついにこの時が来た。声を聴いて、その主を求めて無意識に指先が彷徨う。見えないことにすっかり慣れてしまって、瞳が姿を探すことはないけれど。月の光を反射して、炎の瞳は燃え立つように揺らめくだろう。随分懐かしい気がする。懐かしむほどの時間はきっと過ぎてはいないだろうに。伸ばした手が触れあって、そのぬくもりを確かめれば、ふつふつと胸に湧き上がるのは、あの日一度鎮めたはずの想いだった。)……何処へなりとも。(囁いて、手を取る。今度こそ離さぬように、離れぬように。舞踏のように優雅ではないけれど、友情のように麗しくはないけれど。想いあっていればいいなんて、綺麗ごとね。こんなにも求めている。待っていたの。待っていたのよ。貴女の手を取るその時を。物語の結末を。)
(一冊の日記帳がある。誰のものとも知れないそれには、みみずののたくったような、お世辞にも綺麗とは言えない手蹟が綴られていた。文字は曲がり、重なり、縺れ。ところどころで拾える言葉を繋げてみれば、書き手は女で、目の見えない病を患っていたことくらいは知れるかもしれない。古びた日記帳は、小さな町の、小さな家に置き去られていた。かつてその町には、名も知れぬ二人の娘が手を取り合って生きたという。)
Published:2018/12/29 (Sat) 23:59 [ 34 ]